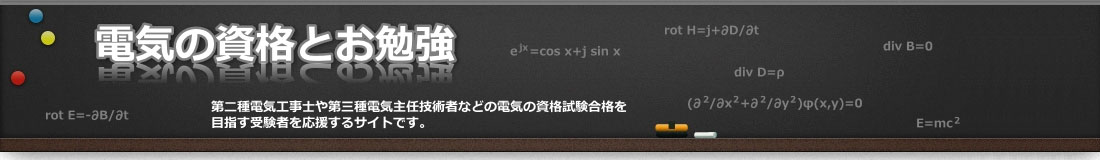スポンサーリンク
電圧・電流・抵抗
※ページ内にPR・広告が含まれる場合があります。
電圧、電流、抵抗という言葉はなんとなくでも聞いたことがあると思いますが、
電圧、電流、抵抗ってなんですか?
と、誰かに聞かれたら何と答えますか?
ここでは、電圧、電流、抵抗について勉強してみましょう。
もくじ
スポンサーリンク
電圧
電圧と聞いてすぐに思いつくのは、乾電池の電圧は1.5V(ボルト)!

コンセントの電圧は100V(ボルト)!
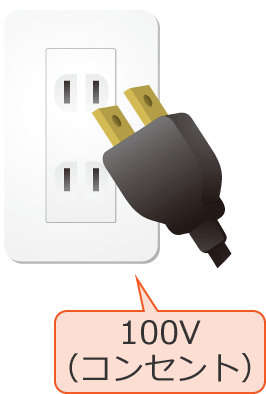
とかでしょうか。他には昔はこんなのもありました。
君のひとみは10000ボルト! −アリス−(かなり危険な状態です…。)
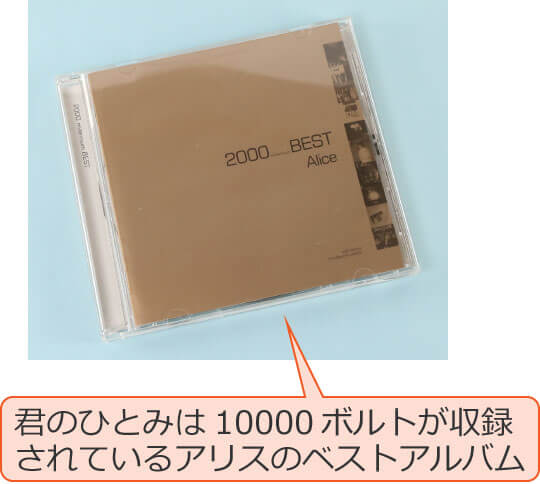
このように、電圧のことをいうときは「○○V(ボルト)」とみんな言っています。
数字の後に付く「V」は「ボルト」と読み、電圧の単位になります。
それから、数字は電圧の大きさを表わすので、数字が大きければ電圧が大きい(大きな電圧)、数字が小さければ電圧が小さい(小さな電圧)ということになります。
ひとまずここでは、
- 数字が大きければ電圧が大きい(大きな電圧)
- 数字が小さければ電圧が小さい(小さな電圧)
- 電圧の単位は V(ボルト)
ということだけおぼえておいてください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
電流
次は、電流です。
電流という言葉は聞いたことがあると思いますが、電圧ほどにはあまりなじみがないかもしれませんね。
よく分からないものは、とりあえずイメージしてみましょう。
電流という言葉を分解すると、「電」と「流」になるのでこれからイメージすると、
電 ← 電気の意味?
流 ← 流れ?
こんな感じになると思います。
この2つの意味を合わせると、電気の流れ?になります。はい、正解です!
電流は「電気の流れ」を意味しているもので、「電流が大きい」とか「電流が小さい」とかいいます。つまり、
「電流が大きい」=「電気がいっぱい流れている」
「電流が小さい」=「電気が少ししか流れていない」
こんな感じになります。
それから、電流にも単位があって、電流の単位は「A」と書いて「アンペア」と読みます。
あれ? アンペアって聞いたことありますよね?
「あなたのお家のブレーカは何アンペア?」
「私のお家は30アンペア!」
このような会話したことありませんか?(なかったらゴメンナサイ! _(._.)_ )
ということで、ここでは、
- 電流が大きい=電気がいっぱい流れている
- 電流が小さい=電気が少ししか流れていない
- 電流の単位は A(アンペア)
ということだけおぼえておいてください。
抵抗
3つめは、抵抗です。
抵抗という言葉は普段の会話でも使う言葉なので、なんとなくイメージできると思いますが、国語辞典で調べてみると、
「外部から加わる力に対して、はむかうこと。さからうこと。」
と書いてあります。
もちろん、国語辞典に書いてある抵抗の意味は「電気の世界の抵抗」の意味ではなく、普段みんなが使っている抵抗の意味なのですが、これは電気の世界の抵抗にもそのままあてはまります。
外部から加わる力 = 電圧
はむかうこと。さからうこと。 → はむかうことをするもの。さからうことをするもの = 抵抗
つまり、抵抗とは、はむかう大きさ、さからう大きさを表わしたものになります。
抵抗についてなんとなくイメージできたと思いますが、抵抗にも単位があり、「Ω」と書いて「オーム」と読みます。
オームと聞いて「オームの法則」を思い浮かべる方もいるかと思いますが、このオームの法則の「オーム」と抵抗の単位の「オーム」は昔々のドイツの偉い学者のオームさんの名前から付けられたものです。
では、抵抗についておさらいですが、
- 抵抗とは、はむかう大きさ、さからう大きさを表わしたもの
- 抵抗の単位は Ω(オーム)
である、ということをおぼえておいてください。
電圧・電流・抵抗の関係
ここまで、電圧、電流、抵抗について解説しましたが、それぞれのイメージができましたか?
ここまででそれぞれのイメージがぼんやりとできれば100点です!(ぼんやり100点! しっかりは150点!!)
次は電圧と電流と抵抗の関係についてちょっとだけ解説します。
先ほどの抵抗の説明のところで出てきた国語辞典の文章について考えます。国語辞典には抵抗の意味が次のように書かれていました。
「外部から加わる力に対して、はむかうこと。さからうこと。」
この文章の「外部から加わる力」が電圧で、「はむかうこと。さからうこと。(はむかうもの。さからうもの。)」が抵抗でした。
では、外部から電圧が加わって、抵抗がさからって…、この結果、何がどうなるのでしょう?
答えを言ってしまうと、電圧の大きさ、抵抗の大きさで電流の大きさが変わります!
な、な、なんと、電圧と電流と抵抗には切っても切れない関係があるではないですか!
この切っても切れない関係を表わしたものが、オームの法則になります。
オームの法則についてはオームの法則のページで解説するので、電圧・電流・抵抗についてはここまで。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
第二種電気工事士(学科試験対策)のTOP ←BACK
NEXT→ オームの法則
スポンサーリンク
電圧・電流・抵抗 関連ページ
- オームの法則
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の計算問題を解くときに使う「オームの法則」についてまとめています。「オームの法則」は電気の計算をするときの一番基本的な法則になりますので、しっかり勉強しておきましょう。
- 電線の抵抗
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の分野で出題される「電線の抵抗」についてまとめています。「電線の抵抗」は第二種電気工事士の学科試験でよく出題される重要な項目ですので、しっかり勉強しておきましょう。
- 直列接続と並列接続
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の計算問題を解くためにおぼえておかなけらばならない「直列接続と並列接続」についてまとめています。「直列接続と並列接続」は電気回路の基本になる接続方法です。
- 合成抵抗
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の分野で出題される「合成抵抗」についてまとめています。第二種電気工事士の学科試験では、「合成抵抗」を求める問題がよく出題されています。
- キルヒホッフの法則
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の計算問題を解くときに使う「キルヒホッフの法則」についてまとめています。「キルヒホッフの法則」は電気の計算をするときの重要な法則になりますので、しっかり勉強しておきましょう。
- 直流回路と交流回路
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の計算問題を解くためにおぼえておかなければならない「直流回路と交流回路」についてまとめています。交流回路の最大値と実効値の関係はとても重要で、学科試験でもたまに出題されています。
- 直流回路の計算(基本)
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の計算問題を解くためにおぼえておかなければならない「直流回路の計算(基本)」についてまとめています。まずは簡単な直流回路の計算をできるようになりましょう。
- 直流回路の計算(分圧と分流)
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の計算問題を解くためにおぼえておかなけらばならない「分圧」と「分流」についてまとめています。「分圧」と「分流」は電気回路の計算をするときの考え方の基本になります。
- 電力・電力量・発熱量
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の計算問題を解くためにおぼえておかなければならない「電力・電力量・発熱量」についてまとめています。電力、電力量、発熱量の違いとそれぞれの求め方をおぼえましょう。
- 正弦波交流波形
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の計算問題を解くときにおぼえておかなければならない「正弦波交流波形」についてまとめています。「正弦波交流」の最大値または実効値を求める問題は試験でも度々出題されていますので、最大値と実効値の関係式は必ずおぼえておきましょう。
- 交流回路の位相
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の問題を解くときにおぼえておかなければならない「交流回路の位相」についてまとめています。「位相」は交流回路の計算をするときにとても重要な考え方です。遅れ位相、進み位相はどのようなものか理解しておきましょう。
- 交流回路のリアクタンス
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の問題を解くときにおぼえておかなければならない「交流回路のリアクタンス」についてまとめています。コイルのリアクタンス(誘導性リアクタンス)とコンデンサのリアクタンス(容量性リアクタンス)の違いをおぼえておきましょう。
- 交流回路のインピーダンス
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」の問題を解くときにおぼえておかなければならない「交流回路のインピーダンス」についてまとめています。インピーダンスというとちょっとむずかしそうですが、おぼえると簡単です。
- 電気でよく使われる単位
- 第二種電気工事士学科試験の「電気理論」分野で出題される「電気でよく使われる単位」についてまとめています。「単位」は電気を勉強するときの基本中の基本になりますので、しっかりおぼえておきましょう。
- 電気でよく使われるギリシャ文字
- 第二種電気工事士学科試験の計算問題などや単位などで使用されるギリシャ文字の読み方と表わす意味についてまとめています。電気の世界に限らず理系の分野では、色々な量を表わしたり、単位の補助記号としてギリシャ文字が使用されますが、代表的なものだけでもおぼえておくようにしましょう。